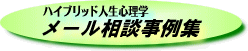 |
はじめに・「取り組み実践」とメール相談 掲載方法について 島野のメール相談活動 代表的事例 テーマ別事例 |
| はじめに・「取り組み実践」とメール相談 ハイブリッド心理学を自身の心と人生のために実際に役立て、生涯を通して心の成長と健康、そして豊かさへと向かうための意識実践の営みを、「取り組み実践」と呼んでいます。 ここでは、この『事例集』でそのさまざまな事例を紹介する「メール相談」(『読者広場』掲示板での相談投稿も含みます)が、そうした「取り組み実践」においてどのように位置づけられるものなのかを、まず説明しておきたいと思います。 「取り組み実践」とは ハイブリッド心理学の「取り組み実践」とは、一言で、「学びの応用思考と向き合いの実践」だと言えます。 つまりそこには、大きく3つの構成要素があることになります。「学び」と「応用思考」、そして「向き合い」です。 ・「学び」 まず「学び」は、ハイブリッド心理学が伝え示すものの、まずは全てを指します。 その中で、「取り組み実践」において特に意識して実践してみて頂きたい事柄を、これまでの著書では「学びの主要テーマ」もしくは「学びの項目」といった言葉で明記しています。改めて、「実践の学び」と呼ぶと分かりやすいかと思います。 その項目立ては、整理の仕方によって多少の増減はありますが、最新の『概説』では、次の6つの項目立てとして整理しています。 「学びの主要テーマ」(「実践の学び」)の6項目
一方、そうした意識的実践によって、私たちの心に起き得る変化とはどのようなものか、そもそもそれに遡り、心の病みとはどのようなものか、そこからの心の健康と成長、さらには豊かさへの歩みとはどんなものか、その全体に向かうための、私たちの心の基礎基盤とはどのようなものかといった、より幅広い「学び」があります。 この幅広い「学び」とは、一言で、上記の意識実践が目指すものについての「学び」です。当然、目指すものが何かを正確に理解するごとに、意識実践もより正確で確実なものになるでしょう。 私の著書ではそれを、主に「歩みの道のり」というタイトルの下で説明しています。ここではそれを、以下5テーマとして手短に記しておきましょう。 「歩みの学び」の5テーマ
このように、ハイブリッド心理学の「学び」は、「実践の学び」の6項目と「歩みの学び」の5テーマという、つごう11個の項目テーマから成るものと覚えておいて頂ければと思います。 ・「応用思考」と「向き合い」 以上のような「学び」を、実際に自分の心と人生に役立てるための意識実践が、「応用思考」と「向き合い」です。 つまり、今目の前の具体的な問題課題場面への対処として、どのようなものが心の成長と健康に向かうために望ましいのか、またそれがどのような人生の視野の下に考えるべきものなのかについて、ハイブリッド心理学からはどのような話が出てくるものなのかを、まず推測展開します。これが「応用思考」です。 次に、それについて、自分としてはどう感じ考えるかを検討します。これが「向き合い」です。 ハイブリッド心理学の「取り組み実践」とは、あくまでこの「応用思考」と「向き合い」を行うことを指します。 読んでどう感心感銘し、どう気持ちが楽になれたとか前向きになれたとかは、もちろんそれは無駄なことではありませんが、まだ「取り組み実践」ではありません。 これは身体の健康のための生活習慣や食事習慣、運動習慣の改善と、何ら変わる話ではありません。自分の体の健康を改善向上させるための方法があることに感銘を受け、気持ちが前向きになれたなら良いとして、気持ちが前向きになれたのだからもういいやとばかりに、実際にその改善法を実践せずに以前と同じ生活習慣のまま、では何の意味もありませんね。 それと全く同じ話です。そうしたものとして、「応用思考」と「向き合い」を行うのが、ハイブリッド心理学の「取り組み実践」です。 自分自身で、独力でです。人に手助けを受けての「応用思考」というのは、厳密には「応用思考」ではなく、「応用の参考例の学び」だと言えるでしょう。また自分としてどう感じ考えるかを明瞭にするという「向き合い」を、自分の代わりに人にやってもらうというのはあり得ませんね。 ですからハイブリッド心理学の「取り組み実践」とは、あくまで独力で行う「学びの応用思考」と「向き合い」の意識作業の営みを指すものです。 内容としては、「外面行動は建設的なもののみ行い、内面感情はただ流し理解する」という「感情と行動の分離」の基本姿勢に立った、外面行動法の検討と自分の内面感情の理解が、「応用思考」と「向き合い」で行うものになります。 順序としては、まずは今自分が置かれた具体的問題課題場面における、「心の健康と成長に向かい得る行動法」の選択肢、そこにおける知恵とノウハウが具体的にどう出てくるのかという、「応用思考」からです。 そしてそれについての自身の理解納得を確認し、自分が今選ぶことのできる行動を決断するための「向き合い」を行います。幾つかの行動の選択肢に対して、自分の内面感情は、どれに向かうことができるものなのか、と。 そしてそこに困難があるほどに、自分の中で何が妨げになっているのかという、心のメカニズムの学びの「応用思考」でもあるところの、内面感情の解きほぐし理解の「向き合い」が必要になってきます。そして解きほぐされた心で、再び、自分が今選択すべき外面行動を、自らに問うのです。 こうした進め方の全体がうまくできない場合は、「自分自身への論理的思考」や「心の依存から自立への転換」といった心の足場テーマについて、今自分に足りないものは何か、必要なものは何かといった「応用思考」と「向き合い」が必要になってきます。ただこれは話も難しくなってきて、メール相談では手があまり出せなくなってくるものでもあります。 こうした「応用思考」と「向き合い」を自己独力で行うことができるごとに、この実践は単に「学ぶ」ことを超えて、未知の心の世界への成長変化へとつながっていきます。 それは自らの心の健康と成長、そして豊かさに向かって、自らを方向づけ前進させることができるという、「現実を生きる力」の増大、それによって感じ取ることができる「内面の力の増大」の感覚であり、埋もれていた感情に出会う、自己の混迷の消失です。 そうして「応用思考」と「向き合い」を経て、新たな自分となった自らの足で、再び人生へと向かう。この積み重ねの先に、日々別の人間へと成長変化していく、歩みの道のりがあります。 こうした「応用思考」と「向き合い」の内容および流れの要点を、下の「「応用思考」と「向き合い」の内容と役割 一覧表」にまとめてみましたので参考頂ければと思います。 「応用思考」と「向き合い」の内容と役割 一覧表
メール相談の役割 ・メール相談は「取り組み実践」ではない 「取り組み実践」とは自己独力による「学びの応用思考と向き合い」だという話から言えるのは、「メール相談」はあくまで「取り組み実践」ではない、ということです。 「メール相談」の役割位置づけについて、私はよく「最初の一歩の手助け」「エンジン始動の手助け」といった言葉で表現しています。 つまりそこには、「自己独力による学びの応用思考と向き合い」であるところの「取り組み実践」と、アドバイザー(島野)による助言を得る作業である「メール相談」とでは、継続のできる期間的長さ、そしてその一歩一歩の歩みが刻むことのできる深さという2点において、大きな違いが出てくることを言うことができます。 この2点の違いを、まずは自分の土地を整備する作業に喩えることができます。 「メール相談」は、自分ではまだせいぜい家庭園芸用のショベル程度しか持っていないため、パワーショベルや掘削機が必要な、自分では無理そうな作業を、高い料金を払って業者を呼んでやってもらう作業に例えられます。 当然、業者にやってもらえることは、時間的量的に限られます。一度多少の整備をしてもらったとしても、土地に根本的な問題があれば、しばらくするとすぐまた土地は荒れ、手に負えなくなってしまいます。業者を呼ぶ回数を増やせればいいという話だけではなく、いつどのように土地が崩れるのかを常に自分で見ていてこそ分かることがあります。結局人の助けには限界があるのです。 それに対し「取り組み実践」は、自らがパワーショベルや掘削機、さらには探知機といった強力な装備と、その操作技術を手に入れて土地の整備をする営みだと言えます。 こうなると話が全然違ってきます。長い歳月を通して継続的に整備の整備に取り組むことで、やがて根本的な問題箇所も見えてきてそれを整えたり、さらにはそうした整備作業の中で、自分の土地に埋もれていた金やダイヤンドの鉱脈を探し当てることも可能になるでしょう。この「金やダイヤンド」がハイブリッド心理学の取り組みにおいて何を指すのかは、ハイブリッド心理学の著書に多くなじんで頂いた方にはお分かりかと思います。それは「魂の望み」の感情です。 ・「人生の歩みそのもの」になり得る「取り組み実践」 継続期間の長さの点では、自己独力による「取り組み実践」は、『ハイブリッド人生心理学 概説』をその言葉で締めたように、人生の歩みそのものになり得るものです。 自分の心と人生に取り組み、悩みと混乱そして動揺を克服して、やがて「魂の望み」の感情に出会い、それに導かれて人生を歩む。それが「取り組み実践」であり、それは人生の歩みそのものになるのです。 この点で「メール相談」を、「人生」と「人生相談」の関係で理解できます。それぞれの人の「人生」があり、それに悩んだ時、人は「人生相談」の門を叩いたりします。それがどう役に立つにせよ、そこから戻って、再び自分で考えて歩むのが、その人の「人生」です。 ハイブリッド心理学のメール相談も、人生相談の一種と言えます。それがどう役に立つにせよ、自分で歩む人生がある。ならばハイブリッド心理学の「取り組み実践」は、その「自分で歩む人生」の側になる、ということです。 そのようなものとして、この心理学を学ぶのであれば、本当に「取り組み実践」をするかどうかが問われる、ということになります。 以前「期間メール相談」などを開設していた時、長くメール相談を続けることが、この心理学への取り組みだと感じておられるらしい印象の方が少なからずおられたの実状です。それではまだ「取り組み実践」にはなっていません。もちろん私にはそんな印象に見えた裏で、実際のところどのように自己独力での取り組み努力を試みておられるかどうかは、私には分かりません。 ・「取り組み実践」の歩みの「深さ」はどこにあるのか ではどのような自己独力の試みになれば、「取り組み実践」になるのか。そのより本質的な違いは、期間的な長さという点よりも、一歩一歩の歩みの深さという点にあります。 「「応用思考」と「向き合い」の内容と役割 一覧表」を再び確認頂ければと思います。そこに、自己独力の取り組み実践の「深さ」の鍵が示されています。 メール相談では通常、悩みの状況について可能な範囲で詳しく書いて頂き、そこから、内面ストレスを減少させながら外面問題をうまく解決できるような、なるべく即効的なポイントや、人生の大きな方向性の選択肢の考え方といった、当面の優先度からのアドバイスを行います。そしてそれがうまく行くようであれば、取り組みの範囲をより広げるための視点、うまく行かないようであればより基本となる心の足場の視点についてアドバイスするのが、メール相談のおおよその一くくりになります。 メール相談のそうした流れによって、「学びの応用思考と向き合い」という「取り組み実践」の意識作業のどの範囲が可能なのかを、表の「メール相談でカバーできる範囲」で凡例表示した枠線によって示しています。 つまり、優先的な問題における「心の健康と成長に向かい得る行動の選択肢」については、「基本的な答え」を、島野から十分に示すことができます。交友や恋愛における行動法にせよ、仕事場面における行動法にせよ、「心の健康と成長に向かい得る行動法」は、「学びの応用思考」としての、幾つかの選択肢の答えが、すぐに出るのです。 一方それに対する「向き合い」、さらには「向き合い」を受けて次に検討すべきテーマといったものになるにつれて、私からの「答え」は、あまり確定的なものは示せなくなってきます。凡例表示に記したように、検討ポイント、つまり選択肢への理解納得や、今選択できるものは何かを見出すための内面向き合いのポイントの、ごくヒントは示せるものへ。さらには、こうした学びのテーマがある、といった示唆程度ができるものへと。 このように書くと、メール相談ではない自己独力の「取り組み実践」の深さとは、「向き合い」の深さにあるのかと感じるかも知れませんが、実は完全に逆なのです。 「取り組み実践」の深さは、「応用思考」の深さにあります。 ・「取り組み実践」の深さとは「応用思考」の深さ どういうことか。つまりメール相談では、相談者がまず自分では「応用思考」をあまりうまくできないため、それをほぼ全部島野が用意してみる、というものになるのです。この点が、自己独力の「取り組み実践」と完全に対照的な部分です。 「向き合い」以降は、実はあまり変わらないのです。自己独力でもメール相談でもです。 これは少し考えてみると、当然であるのが分かると思います。つまり、「今この問題については、学びからはこうなる」という「応用思考」がもし出されるならば、それについての「向き合い」はごく自然と起きるのです。それぞれの人なりに。自己独力であったとしても、メール相談であったとしても。それが自己の心の奥深くの琴線をどのように震わせ、心を変化させるかは次の話として。 そのようなものとして、まずは「学びの応用思考」が言葉として人から用意されるのがメール相談であり、自己独力で用意するのが、「取り組み実践」なのです。 そうしてとにかく「学びの応用思考」が言葉として用意されたとして、次の「向き合い」が、メール相談よりも自己独力の方がより深いものになるのかというと、私自身考えてみて、さて・・と考えあぐねるような、良く分からないことなのです。 つまりそれについては幾らでもバリエーションがあるのです。メール相談の中で、私が示したごく僅かな示唆に対して、ご相談者が、私の予期よりよりもはるかに深い向き合いに向かった場面も少なくありません。一方私自身の歩みの中でも、「今この状況はこんな話だということか・・」と自分で考えた「学び(カレン・ホーナイなり認知療法なり)の応用思考」の内容は正しいながらも、それを基にした自己向き合いは、自分へのポーズのような上辺だけのものになったり、あるいは「僕には今はそうはとても感じられない!」と、「学び」とのギャップの自覚に向かったのもざらです。 つまり結論は、引き続き土地の整備の喩えで言えば、パワーショベルと掘削機が「応用思考」であり、探知機が「向き合い」だとして、歩みの深さを生み出すのは、まずはパワーショベルと掘削機なのだ、ということです。 探知機である「向き合い」の深さというのは、まずはパワーショベルと掘削機である「応用思考」があってのことであり、その上で、探知機の能力性能として、その人がそれまでの人生で培ってきた「自分自身への感受性」と呼べるものと、「向き合い」の積み重ね体験による感度の向上が、最終的に生み出す。そのように言えると思われます。 ・深い「向き合い」が生み出す「パラドックス前進」 そこでの「向き合い」の深さについて言えば、それはとにかく「学び」が示すように感じられればいい、というものなどでは全くありません。むしろ、自分がどのように「学び」が示すものとは異なるものへと向いているかという、「ギャップの自覚」こそが、「ありのままの自分自身への感受性」の入り口でもあり、それが逆に「学び」が示す道へとその人を近づけるという、「パラドックス前進」と呼んでいる歩みの姿があります。これについては『概説』や『取り組み実践詳説』で詳しく解説していますので参照頂ければと思います。 つまり、自分の目でしっかりと心の健康と成長を見据えながらも、そうは絵に描いたようには動いてくれない自分の心を見つめる苦しみこそが、実は私たちを、「自意識のあがき」を超えて、心の健康と成長へ変化させるのです。 自己独力の「学びの応用思考」が、やはりその入り口であり、それこそが、パワーショベルと掘削機と探知機が一体化した、真の深さを生み出す歩みだと言えます。 こうして、まず「学びの応用思考」を自己独力でできることこそが、「向き合い」とも一体化して、歩みの深さを生み出し、生涯にわたる歩みという期間的な長さをも合わせることで、やがてはまるで別人のように豊かさで安定した心へと成長変化していく、歩みの道のりがある。 それがハイブリッド心理学の「取り組み実践」の歩みであることを、まずはご理解頂ければと思います。 自己独力での「学びの応用思考」へ ・「学びの応用思考」の正確さが取り組み実践の「命」 では自己独力で「学びの応用思考」を進めるためのポイントはどのようなものかに話を進めましょう。 まず何を置いても重要なのは、「この場合ハイブリッド心理学の学びからの応用としてはこうなる」という「応用思考」の結果内容の、「正しさ」「正確さ」です。 もちろん、ハイブリッド心理学としての「正しさ」「正確さ」です。 これがないと、ハイブリッド心理学の「取り組み実践」は始まりません。この点では、「とにかくまずやってみることが大切」ではなく、「正しい内容を理解する」ことが、全ての始まりとして重要になります。 これは例えば、『取り組み実践詳説』の「8章 「全てを尽くして望みに向かう姿勢」を培う」で紹介した、スーパーの駐車場で誰かにつけられている気がして精神的におかしくなりそう、という相談事例(P.144)などでも、良く分かるかと思います。 これはメール相談ではなく、インターネット上の悩み相談コーナーへの相談投稿に私がアドバイス投稿をしたものですが、「気にしないようになれればいいのだろうが」という心づもりで書いておられるらしいその相談に、「気にしないこと」ではなく、「全力で戦うべき場面」として対処することが課題だと示唆し、実際まず行うのが良いであろう防犯対策行動を幾つかアドバイスしたところ、ご相談者は目から鱗が落ちたかのような様子の言葉として、「実践してみます!」と返礼を返してきたものです。 もちろんこのケースでは、ご相談者は事前にハイブリッド心理学には接してなかった訳ですが、ともかくご相談者なりの心理学の応用思考としては、「気にしなくなれることが課題か」というようなものであり、ハイブリッド心理学からの「全力で戦う姿勢が課題」というものとは、思考が最初に完全に逆方向を向いていたわけです。 このように「具体的場面での応用思考」の内容が正しくないと、その先の意識実践をどう続けても意味がないのは明らかです。事態が打開しないばかりか、場合によってはさらに事態を悪くしてしまいます。 「学びの応用思考の正確さ」が、取り組み実践の「命」だと言えます。 それはパワーショベルと掘削機を土地に打ち込む、正確さです。それが全ての始まりです。それがなければ、むやみにパワーショベルで宙をかき、掘削機で宙を打つだけになってしまいます。 ・人の言葉で変われるのは「すでに準備されている潜在的成長力」の引き出し 実は、そうした例とほとんど同じことを行っているのが、ハイブリッド心理学のメール相談です。 つまりご相談者は多少ともハイブリッド心理学に接してから相談を寄せるのですが、いざ自身の具体的問題に際してハイブリッド心理学からはどうなるのかは、自分ではほとんど考えつかない、もしくは考えた内容が誤った方向にありうまく進めないという状況で、相談を寄せてこられます。 で、まずは島野から、正しい「応用思考」としてはこうなるというのを示す、ということを行うわけです。すると次の「向き合い」は、その人なりに可能なものが、可能な範囲で、自然に起きます。 これは長くメール相談を行った方でも同じです。長く続けても、自分ではなかなか正確な「学びの応用思考」ができない形で、相談を寄せるという形です。もっとも、自分で正確な「学びの応用思考」ができた場合は、相談は送って来ていないかも知れませんね。 いずれにせよ、長くメール相談を続けるほど、皮肉なことに、メール相談の効果が見られなくなるという印象を感じたのが実情です。 そうなる理由があります。人の言葉に感銘を受けて変わることができるというのは、実はその人に潜在的に準備されていた成長が、その言葉によって引き出されたものだ、ということです。 ハイブリッド心理学のメール相談が役立つとすれば、それはやはり、その人にすでに準備されている潜在的成長力を、引き出すものとしてだということです。ハイブリッド心理学のアプローチが範囲とするものにおいて。 以前行った「期間メール相談」では、そのために要するのは大体1、2か月、最も長くてもせいぜい半年以下という印象です。つまり逆に言えば、メール相談をいくら頻繁にじっくり行ったとしても、効果があるのは、大体1、2か月程度、最も長くてもせいぜい半年以下だということです。長く続ければ続けるほど良い、というものではないのは明白です。 ・「新たな潜在的成長力をこれから準備していく」という取り組みへ 人の言葉、つまりメール相談における島野の言葉によって変われる部分が一段落したら、進め方を変える必要がある、ということになります。さらなる成長を目指すのであれば。 そうした段階を過ぎてなおメ−ル相談を続けようとすることは、実は単に効果が出なくなってくるということだけではなく、新たな歩みに向かうことを阻害する姿勢にもつながってきます。かくして、この人のメール相談にはもう効果がない、という印象が私にもはっきり見えてくる、というものになったようです。 さらなる成長を目指すのであれば、人の言葉で変わるというものを超えて、自らの言葉で自身の成長を引き出す・・否、まず自身の言葉で次の潜在的成長力をこれから準備していくための、取り組みに向かう必要があるのです。 そうして準備されていく次の成長を引き出すのは、言葉によって、という安直なものではなく、人生を生きる実際の体験によって、という大きく深いものになる。そのようなものとしてです。 それが、まず自己独力でハイブリッド心理学の正確な「学びの応用思考」を考えてみる、という取り組みです。 ・感情改善を目的にすると取り組み実践は失敗する それをどのように行えばいいか、まず逆に、多くの人がそれができない理由から説明したいと思います。 それはずばり、取り組み実践を「感情の改善」を目的に行おうとしてしまうことにあると思われます。 取り組み実践の目的は「感情の改善」ではありません。行動法と価値観、そして生き方姿勢の確認と検討が目的です。 これは身体の病気や怪我で考えると分かりやすいと思います。私たちは体の痛みや不快感で病気や怪我を知るのですが、その治療は「痛みを取り去る作業」よりも、「痛みの原因(これが病気や怪我そのもの)を取り去る作業」です。もちろん痛みを取り去ることも補助的に有益ですが、痛みを取り去ることばかりに気が取られて、痛みの原因となる病気や怪我の正体とその治療への理解がないままでは、いつまでも治せず、結局取り去りたい痛みも取り去れないままになってしまいます。 同様に、感情の動揺や悪感情の存在によって、私たちが自らの心に課題があることを知ったならば、短絡的に悪感情を取り去ろうとするのではなく、その原因となる思考法行動法や価値観、そして生き方姿勢に取り組むことが大切です。痛みを伴う治療があるように、痛みを伴う成長もあるのですから。 ・・とここまでの話は良いのではないかと思います。で、まさにこうしたハイブリッド心理学の言葉に感心して、多くの方がメール相談を寄せてくるわけです。自分では「正確な学びの応用思考」がうまくできずに・・。 何が起きているのかと言うと、悪感情を短絡的に取り除こうとするのではなく、原因となる思考法行動法そして価値観と生き方姿勢に取り組むという話には納得していたとしても、いざ具体的問題に際しての「学びの応用思考」をしようとすると、結局再び感情がどう良くなるかを基準に、思考しようとしてしまうということではないかと思います。 つまり、「学びの応用思考」を、やはり、「とにかく今より少しでも良く感じられるもの」としてはどうだろうか、という姿勢で思考してしまうことにあるのではないかと。 それでは結局、ここで説明してきた「取り組み実践」になりません。 つまり、今よりそれがどう良く感じられるかどうかは、「向き合い」の段で検討すればいいのです。それを、「学びの応用思考」の段階で同時にやろうとする。そうしてどう感じられるかによって「学びの応用思考」を考えようとうすると、「学びの応用思考」が失敗します。それは結局、今の感情の中、今の心の中だけで、考えようとすることだからです。 それによって結局、取り組み実践そのものが失敗するのです。 ・「どう感じるか」を抜きに「学びの応用思考」を作る ですので指針としては、まずは「それをどう感じるか」を全く抜きに、「学びの応用思考」を作ってみる、という実践です。 これについて私は最近、「国語のエクササイズ的に」という表現をしています。これこれの者がこれこれの状況に置かれた。そこにおける「破壊」「自衛」「建設」の各行動様式の行動を、具体的に述べよ。そんな感じになりますね。 そこから、ていねいな「向き合い」を進めることができるでしょう。 あるいは、「言葉」をうまく駆使して「自分自身への論理的思考」をするという、基礎中の基礎の心の足場への取り組みの必要性が、そこでクローズアップされてくるかも知れません。基本的に感情でものごとを考える、そして他人の思考を借りる(自分では思考できない)という、現代人がどっぷりと慣れっこになった傾向という壁が、そこにあると言えるかも知れません。それとは異なる、荒波の中に碇のように下せる思考を、いかに自分自身でできるようになるか。それが、「動揺する感情を克服したいなら、まず感情を鵜呑みにして考えない」という、取り組みの全ての始まりになります。 ・3つのレベルの奥深さで歩む「取り組み実践」 具体的な内容に話を移せば、メール相談の中で十分に答えを示せるというものとして「「応用思考」と「向き合い」の内容と役割 一覧表」に示した「外面行動法の応用思考」が、そこに記した、 −心の健康と成長に向かい得る行動の選択肢 というもののごく外面的内容だけではなく、 −その支えとなる「価値観」と意識姿勢、生き方姿勢、また −長い人生(「命の生涯」)という視点からの向かい方の視野 という、大きく3つのレベルの奥深さから成るものになることを、まず理解頂くと良いでしょう。それらが、目の前の場面での具体的行動、年単位で常に念頭に置き検討すべきテーマ、そして到達は分からないながらも自らを方向づけたい、遥かなる目標という位置づけになります。 そこで重要なのは、「今自分にとって問題は何か」がはっきりすれば、上記3つの深さのレベルにまたがる、ハイブリッド心理学からの学びの応用の答えが、明瞭に示される、ということです。 そこでしばしば問題になるのが、それぞれの方にとって今一体何が本当の問題なのかが、それぞれの人の中で、それぞれの人自身に、あいまいになったり、誤魔化され紛らわされたりすることです。 かくして、問題がはっきりしていれば答えとなる行動の選択肢について、問題がはっきりしなければ一体何が問題なのかへの、「向き合い」の段階が始まり、その補助になるものとして「内面感情の応用思考」、つまり心理メカニズムからはこうしたものが問題課題と考えられるといった応用思考ができ、さらにそれについての「向き合い」を進め、自分の心の奥深くへの解きほぐしが進む、という流れになります。 これを、生涯にわかり、人生の歩みそのものとして行っていくのが、ハイブリッド心理学の「取り組み実践」になるわけです。 それを全て自己独力でとは言っても、最初の段階は自分で考えてみようとしてもなかなか思い浮かばないかも知れません。 いいでしょう。そのために、私はこの『事例集』をまとめることにしました。できるだけ多くの事例に触れることで「この場合の学びの応用はこうなる」という、おおよその方向性がつかめてくるのではないかと思います。 一方で、ハイブリッド心理学の著書全般について、一気に読んで「習得」しようと焦るのではなく、日々時間の折に、じっくりと自らの理解納得を問いながら少しづつ読む習慣を持つようにして頂くと良いでしょう。これは心の懐の引き出しをより豊富なものにすることに役立ちます。 そうして「取り組み実践」は、 1)定常的な読書の習慣 2)日々出会う問題課題に際しての「学びの応用思考と向き合い」の実践 という、「二頭立て」の意識実践として営まれる、というものになります。 メール相談を超えて その先の流れについても少し書いておきましょう。 ハイブリッド心理学では、以上説明したような「学びの応用思考と向き合い」としての「取り組み実践」が、変わることのない一本調子で生涯続く・・とは考えていません。 大きな節目と、それにより大きく一変する歩みの様相という、大きな2つの局面があることを考えています。 その大きな節目が、「実践の学び」の6項目の最後であり総仕上げ的なものとして位置づけられる、「否定価値の放棄」に、他なりません。 ・「否定価値の放棄」への歩み それはこのような流れのものになります。 まずあるのは、「実践の学び」の頭からの4項目、つまり「感情と行動の分離」の基本姿勢、行動の基本様式の「破壊から自衛と建設への選択」、「行動学」、そして「愛」と「自尊心」のための価値観と行動法という、比較的外面行動法寄りのテーマについて、それらの「学び」そのものへの自身の理解納得について向き合うと共に、具体的場面での「心の健康と成長に向かい得る行動法」について、具体的な「学びの応用思考」が自分でできるようになる、そして実際その行動法の実践を積み重ねていく、という「習得」「習熟」の過程です。 そしてそれを基本的な前進の足場として、次にあるのが、「社会を生きる自信」を、「現実において生み出す」という自己の実績によって得ていく、人生の道のりです。これは特に、「仕事の普遍的スキル」なども含む「行動学」と、「自尊心」のための価値観における取り組みになります。 そうして「社会を生きる自信」というしっかりとした裏打ちのある、「真の強さ」というものを自分が得始めたという段階になって、いよいよ、「否定価値の放棄」という、「実践の学び」の最後の、核心となるテーマに向き合うことができる。これがハイブリッド心理学の考えです。その最後の「選択」を決するのは、そこに至るための「真の強さ」への歩みが外面行動法の学びに重きを置いていたのから一転して、「信仰」についての自分の考え方への向き合いも経て、「弱さ」が今まで生み出し続けていた、自分が「神」のような絶対的な存在になろうとする無意識深層の衝動に気づき捨て去るという、哲学宗教的とも言える内面的な向き合いになる、と。 こうした歩みの道筋については、『概説』、さらに詳しくは『取り組み実践詳説』などを参考いただければと思います。 「否定価値の放棄」は、「自分から不幸になろうとする」という私たち人間の「心の業」、「自意識の業」の根源の捨て去りでもある、とハイブリッド心理学では考えています。 この捨て去りにより、私たちの心のあり方が一変します。それは私自身の体験で言えば、「別の人間になる」というよりも、「別の種類の動物になる」と言えるような、大きな変化です。私が今感じる表現をするならば、私たちはそれによって、「人間」という檻から解き放たれた、新たな動物になるのだ、と。 これにより、「実践の学び」の項目説明の中にも記したように、心のプラスエネルギーが大きく開放されます。 それは「望み」の感情という心のプラスエネルギーでもあります。それに向かって、それまでに培った建設的行動法によって、引き続き歩んでいくのです。 「否定価値の放棄」へと至ることは、同時に、ハイブリッド心理学の「取り組み実践」における「習得」「習熟」の段階が、ほぼ全て完了したことを意味します。 そこからの歩みは、大きく開放される「望み」に向かって、習得習熟済みの建設的行動法によって引き続き歩んでいく。そこではもう「この場合での建設的行動法とはどのようなものか」と「学ぶ」ような段階ではないということです。もしそれがまだ必要であれば、歩みの全体が「否定価値の放棄」のかなり前の、まだ前半段階にあるということです。 重要なのは、今説明した流れの中で、建設的な行動法と価値観を自らのものにするのが、抜けの全くない、ほぼ100パーセントへと至ることです。それを足場にしてこそ、「否定価値の放棄」という、最後の実践テーマの核心部分に向き合うことができます。それだけが、ハイブリッド心理学の知る道筋です。 その点で、取り組みを始められる方がまず取り組まなければならないものとしては、自分で思考するのが苦手だったり、頭では分かっているつもりといった浅い思考の空回り、あるいは「学び」へのおおむねの理解納得をしているつもりでいて、時と場合によって実は「学び」とははっきり逆の思考と行動を取ることがある、といった状況になるでしょう。「本当のところ自分ではどう考えているのか?」と自分に問い、見えてくるものをしっかり言葉にして日記などに書くといった実践、そして「学び」とは別のものを自分がどう取ろうとしているのかの自覚こそが、「パラドックス前進」として何よりも重要になってくるでしょう。 ・「命の生涯」の歩みへ こうして「否定価値の放棄」を過ぎてからの後半段階の取り組み実践は、「学びの応用思考」についやす労力はなくなっていき、力強さを飛躍的に増した外面行動による人生の前進と、その都度都度における自身の内面感情への向き合いがメインのものになってきます。 心の変化は、前半段階に比べ、異次元に大きく、かつ神秘的なものになってきます。ここではそれをあれこれ説明するよりも、『取り組み実践詳説』の中で使った喩えで言っておくので良いでしょう。前半段階における変化とは、車の運転の教習所の中での習得向上の変化であり、後半段階における変化とは、運転免許を得て教習所の外の世界に出て、自分の人生を旅する変化なのだ、と。 ひとつだけ説明を加えておくならば、異次元の大きな変化とは、「未熟の愛から旅立ち、自立の自尊心を経て、成熟の愛に向かう」という、ハイブリッド心理学が「命の生涯」と呼んでいる変遷にかかわる変化です。 実はこの取り組みの全体が、この大きな変遷の中にあると言えます。自分の考えを持ち、自分の足で前に歩くことから始め、「社会を生きる自信」と「真の強さ」を得て、やがて「否定価値の放棄」を自らに問うという歩みが、その始まりにおいて「未熟の愛からの旅立ち」という側面をどのように意識するかは人それぞれながらも、まずは「自立の自尊心」の確立としてあるものとしてです。これが取り組みの歩みの前半であり、人生の前半だとも言えるでしょう。 そして「否定価値の放棄」によって大きく開放される「望み」のプラスエネルギーによって、「成熟の愛」へと向かうのです。これが取り組みの歩みの後半であり、人生の後半とも言えます。 そこでハイブリッド心理学が見出すのは、「自意識の業」の捨て去りでもある「否定価値の放棄」によって解放される「望み」が、やがて「自分」というものを超越してくるという、神秘性です。 それは「魂の愛への望み」とこの心理学が呼んでいる、命の重みのある、純粋な感情です。それによって、「未熟の愛」の中で人が抱くことになった、「根源的な自己否定感情と孤独感」といった、心の問題の根源の最終的な克服も、この後半の段階で訪れることになります。そこにこそ、ハイブリッド心理学が伝えたい、心の劇的かつ神秘的な変化の世界があります。「永遠の命の感性」とこの心理学が呼ぶ、心の成熟のゴールの領域を特徴づけるものも、その一つとして。 その時私たちは、人間の心の変遷の全体が、「未熟の愛から旅立ち、成熟の愛へと向かう」という、「愛への望み」を単一軸とした流れの中にあることを、その真実の姿を、知ることになります。この心理学において「否定価値の放棄」として完成される「自立の自尊心」は、そのための最大の足場であるにすぎないのです。 無論、メール相談はこうした取り組みの歩みの全体までは、全くカバーするものではありません。その役割について最初に述べた通り、あくまで「最初の一歩の手助け」「エンジン始動の手助け」の部分だけです。 その点で、取り組みの歩みの全体の事例として私がお伝えできるのは、私自身の人生という、たった一つの事例になります。これについては今後『日記ブログ』などの形で整理していきたいと思っています。 そうした神秘的な心の変化の実際の姿を知り、取り組みの歩みの道のりの先に興味を持っていただくもの良いでしょう。 それでも私たちはまず、極めて地道な取り組みから始める必要があります。「学びの応用思考」を正確に習得し、それに対する自分自身の考えを明確にしていくことからです。 そのために役に立つ相談事例を、私はこの事例集で全てまとめていきたいと思っています。 では、始めましょう。 2015.2.27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||