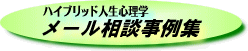 |
はじめに・「取り組み実践」とメール相談 掲載方法について 島野のメール相談活動 代表的事例 テーマ別事例 |
| No.002 視線恐怖および「職場での自分の位置への不安」の克服 アドバイス内容(1) | |||||||
| この事例では、当初「一往復メール相談」として寄せられたこともあり、最初のアドバイスとしては、頂いた文面から見える範囲での、ハイブリッド心理学からのアプローチ概要を伝えるという主旨のものになります。 ハイブリッド心理学についてまだほとんど知らない方も念頭に、「成長」がアプローチになるという、ごく基本的な話からです。合わせて、職場における自分の位置不安、そして街では人の視線が気になるという問題について、「一往復メール」としてまとめられることを、まずは以下のように伝えています。 1回目アドバイス 2010.10.6(水) 特別補足解説:「現実を見る目」の真髄とは
ということで、基本指針としては「ストレスを取り去る」ではなく「成長に向かう」、仕事場面については、仕事の内容に応じた本格的ノウハウ、道を歩く場面での人の視線については「観察精度を高めていく」という、ハイブリッド心理学からのアプローチのごく概要をお伝えしたものです。実際に進めるためには期間相談をお勧めします、と。 それに対しNo.002さんは、期間相談への変更希望と共に、仕事の詳しい内容と状況、さらに道を歩く場面についてはさっそく「どんな幅の道で相手がどのように動いてそう感じるのか」の厳密な観察の実践を始めてみたことを伝えてきました。 それらはもちろん取り組みのための詳細な材料確認であると同時に、興味深いのは、この段階ですでにNo.002さんの心の状態に変化が起き始めたことです。特に、道を歩く場面について。 一方仕事場面についてはもっぱらご自身が感じる困難状況を伝えてくるものですが、そこには同時に、仕事面でも短期間で目覚しい好転変化へと向かうための心の足場がすでにあることが示されています。 それは何なのかにぜひ目を向けて頂くと良いでしょう。 ご相談者返信(抜粋編集) 2010.10.12(火) まず仕事面について、仕事の内容およびご自身の状況についてより詳しく述べたものです。少し長くなりますが、仕事の内容については概要表現に編集した上で、ご自身なりの状況分析をしておられる様子を紹介しましょう。
次に、道を歩く場面で、客観的基準の想定および観察精度を高めるという実践をさっそくしてみたものを報告してこられました。 これも少し長くなりますが、事実こうした細かい事実情報に取り組むのが、「気持ち」「姿勢論」ではなく「現実を見る目」を基盤とする、ハイブリッド心理学ならではの取り組み実践として良いものです。
特別補足解説:「現実を見る目」の真髄とは こうして、No.002さんの「仕事の場面」および「道を歩く場面」という2つの問題状況について、ハイブリッド心理学からの具体的な視点のアドバイスをするための十分な糸口情報が出たと共に、No.002さんに早くも変化が起き始めたのを見ることができます。まずは「やってみて気づいたが、今までは気持ちの動揺が大きくて冷静に見れていなかった。それが意識的に観察しようとすると少し感情に圧倒されずに見れる」という言葉にです。 もちろんこうした即座の好転変化は、似たような問題状況への似たようなアドバイスで、誰にでも起きるものではなく、むしろNo.002さんが特例の部類だとも言えます。 そうならしめたのが、まずは「現実を見る目」に他ならない、ということになります。『実践詳説』などでも「全ての始まり」として指摘したものです(P.69)。 その真髄とは何かが、このNo.002さん事例に示されるでしょう。つまりそれは、「人にこう見られこんな扱いを受けた!」という「空想による解釈」が生み出す心の動揺に流されないために、そこに起きたのはまずは何メートル幅の道で人が何メートル近づいてきたという客観的事実に過ぎないという「空想と現実の区別」をするのに加えて、さらにその客観的事実についての、新しい、より健全で、この現実世界をよりうまく生きるのに役立つような、知恵を得ていくということにあるのです。 「感情を鵜呑みにしないというのが良く分からない」という多くの方の原因が、この真髄部分の不足にあります。 つまり、「感情を鵜呑みにしない」のが良いというのは分かる、そして「こう扱われた!」という感情動揺が空想で解釈した反応であり、客観的事実として起きたのはこれこれに過ぎないというのも分かる、というところまでは大抵の人が行けるのですが、その先の、「客観的事実についての新しい知恵」を持つところまでは行かない結果、「やはりそうとしか考えられない!」という「感情による決めつけ思考」に、戻ってしまうのです。 No.002さんも、この最初の自主的実践の報告では、まだその段階です。だから客観的観察はできていても、「なぜこのような行為をするのか理解不能です」となる。 それでも、「意識的に観察しようとすると少し感情に圧倒されずに見れる」という言葉に、今までの、空想による解釈とは違うものを見つけようとする意志という、「現実を見る目」の真髄の心の土台が、No.002さんにあることを推測できるのではないかと思います。 その新たな知恵を、まさにこのメ−ル相談が提供するものになります。それがNo.002さんを、目覚しい好転変化へと変えていく、という流れになります。 メール相談で効果が出ないケースについても、少し説明を加えておきましょう。 それは「空想と現実の区別」がそもそもできていない、あるいはそれはできていても、「客観的現実についての新しい知恵」への姿勢が持てない、というもののいずれかということになります。 そこでまず正真正銘空想と現実の区別ができないというのは、「妄想憑依状態」あるいは「精神統合失調症」などと呼ばれる、心の障害傾向としても一段階深刻で質の異なる問題が関わり、ハイブリッド心理学のメール相談などでは手が出せなくなるという印象を感じます。 また「新しい知恵への姿勢」が持てないというケースは、もう一つの心の基盤である「心の自立から依存への転換」が同時に不足しているという状況がやはり考えられます。心の土台からして、人にどう見られどう扱われるかが重要だという感情の虜状態であるため、新しい知恵と新しい生き方に向かうという姿勢が持てないまま、「こう見られた!」という空想と感情が湧けば心がそれに占領されてしまいがちです。この場合、「では自分ではどう考えるのか」という、自己起点での思考に取り組むことが(これを「自己の重心」と呼んでいます)、「心の自立から依存への転換」を促すものとして重要になってきます。 「空想の重み」が膨張する心の状態はまた、「現実覚醒レベルの低下」とハイブリッド心理学で捉える、心の障害症状としても起き得ます。 これは一言で、本人にとって「破滅的自己否定感情」と言えるような悪感情を心の奥底に切り離す代わりに、「現実感」が低下した「半夢状態」に意識が置かれるというものです。そこで同時に、「空想の世界こそが真実」だとする、事例No.001でも触れた「自己操縦心性」のメカニズムが働きます。 詳しい話は置いといて、理解のポイントは、このメカニズムは、上記の「妄想憑依状態」「精神統合失調症」でなくとも、一般的な心の動揺状態の深刻なケースでも働くことがあるということです。 その結果、「現実に向き合う」という前進が、この心のメカニズムを突き崩し、いったん「破滅的自己否定感情」が心の表面に膿のように出てから、健康な心の状態が回復するという流れが起きることがあります。これを「自己操縦心性の崩壊の治癒」と呼んでいます。 「自分はもう駄目だ」という絶望感が、まさに、今までの病んだ心が崩壊し消え去り、新たな健康な心が再生する通過点になり得るということです。それをただやり過ごすという姿勢が重要になってきます。 No.002さんの場合、こうした根深い問題は、表面の幅広い困難の様子に比べ比較的経度、もしくはそれを打ち破るための心の足場が実はすでに準備されていたと言えるでしょう。 それは何かが、仕事面でもやがて目覚しい好転変化に向かうことになった、最大の足場と私が見るものの中にあります。 それは自分への正直さ、自分の望みへのストレートさといったものです。「私には職業も家庭も、何もかも人並みにできないのだと絶望的になってしまう。それでも私は諦めたくないのです」といった言葉に示されるように。 No.002さんの言葉が、基本的に問題を自分にあるものと認識しているものであることに注目して頂くと良いでしょう。「自己起点」でものごとを考える、「自己の重心」が持てているわけです。これがまず問題が他人にありそれにどう対処したら良いか、という相談の言葉になってくると、表面の言葉のしっかりした印象と裏腹に、なかなか前進が見出せないものになりがちです。 上記のNo.002さんの最後の言葉、「カウンセリングの先生の前で格好をつけても仕方ないと思いますので偽りの無い自分の現状を書いてみました」という言葉も、印象深いものがあります。 そうでなしに、格好をつけようとするものであるかどうかはさておき、自身が感じる問題をありのままに伝えてアドバイスを求めるというのではなく、自身が感じる問題の核心を伝えないまま解決法を求める、あるいは何か駆け引きのようなものとして話を進めようとしているものであることが、やがて判明してくるといった例が、実は少なからずあったのが実情です。この場合は、メール相談が成立しなくなります。問題のありのままの姿を知り、それに対する、根本的な克服への道を示すのが、私のアドバイスのやり方だからです。 メール相談で効果が出るものとそうでないものについて、心の足場の違いの話が少し長くなりました。 ともかくNo.002さんの事例は、表面の困難の広さに比べ、心の足場は実は健強なものがあったという点をまず参考として頂いた上で、実際に前進を生み出すための具体的な知恵とノウハウがどのようなものか、この後の話をじっくり参考頂くと良いでしょう。 2回目アドバイスヘ 2015.5.5 |