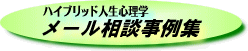 |
はじめに・「取り組み実践」とメール相談 掲載方法について 島野のメール相談活動 代表的事例 テーマ別事例 |
| No.002 視線恐怖および「職場での自分の位置への不安」の克服 アドバイス内容(3) | |||||
| 1回目アドバイス: 「仕事場面」と「道を歩く場面」の問題へのアプローチ概要 2010.10.6(水) 2回目アドバイス: 「仕事のスキルの基本」と「人の空間認知の理解」 2010.10.16(土) 3回目アドバイス 2010.10.23(土)
要点としては、まず自分の誤りを知ることを、「恥」ではなく、「成長の機会」として喜べるように。実際そう感じられるかはさておき、まずそうした心のあり方が成長に向いているものであることを、知ることからです。 職場で信用を失っている状況の挽回においては、それにより対処行動法が変わってくるものとして、状況の深刻度を見定める。「状況出来事」として、現実に起きていることは何かです。 解雇を示唆されたというようなものであれば、自分が信用を失っていることを、話し合い内容として取り上げ、自分がどう変わろうとしているかを伝えるなど。そうではなく、ただ上司や同僚の気持ちとして信頼してもらえていないというものであれば、それについて話し合うというよりも、信頼されるような仕事の進め方およびスキルへの実践あるのみです。 前者の場合も当然、話し合いの後に後者の場合の実践対処が必要です。ですので深刻度により対処行動法が変わってくるというよりも、深刻度により行動対処の内容が追加されてくる、と言うのが正確でしょう。 こうした、問題の深刻度に応じた行動対処法といったものも、「行動学」の一つと言えます。 道を歩く場面については、「客観的な観察の精度向上」と「客観的事実についての新たな知恵」に引き続き、ここで「相手の表情を確認する」というのを、「嫌がらせされる」という感情解釈の脱却の仕上げのようなものとしてアドバイスしています。 この順番に意味があることを、ぜひ理解頂ければと思います。「感情による決めつけ解釈」とは全く別の軸となる、「客観的事実への目と知恵」を十分に持った上で、前者の解釈の真偽の、最終的判断をするということです。そうでないと、結局「やはりそうとしか思えない!」という感情解釈に戻ってしまうことは、1回目アドバイスの「特別補足解説:「現実を見る目」の真髄とは」でも述べた通りです。 「客観的事実への目と知恵」によって、「感情による決めつけ解釈」を頭から無視し否定する、というのでもないことに注意下さい。人の空間認知の差を理解し、相手が問題ない距離で近づいてきたとして、明らかにこっちのことを凝視しているとなると、また話が違ってきます。 いずれにせよ、まず感情に揺らぐことなく客観的現実を見る目を築いた上で、私たちは再度、感情に揺らぐ自分の内面に向き合うのです。感情の動揺が最終的に克服されるのは、この最後の段階です。これが、ハイブリッド心理学の心の外面と内面、2面取り組みです。 「相手の表情を確認する」というのは、相手の物理的距離を確認するというのに比べ、自身の内面感情にかなり影響を受けやすいものと言えます。それで、これを最終的な確認ステップにするわけです。 No.002さんからの返信は5日後で、仕事場および道を歩く場面の双方について、より詳しい状況観察をした結果を伝えてくるものでした。 仕事場での状況が、好転し始めたらしい様子。また道を歩く場面では、問題の解消がほぼ決定的になってきた様子をです。 ご相談者返信(抜粋編集) 2010.10.28(木)
ということで、職場ではとりあえず身の振り方が問われるような深刻な状況ではない様子。さらに、上司のNo.002さんへの態度も以前より柔らかくなってきたと、多少とも状況が好転したようです。 ただしこの時点では、スキル向上のための実践はまだあまり着手できてはいませんので、上司の態度の軟化は、まずはNo.002さんの過剰なマイナス反応姿勢が全般的になくなってきた結果と考えるのが妥当と思われます。また上司自身の内面問題としても、部下への乱暴な言葉を反省し、もっと柔らかい態度で接するにしたといったこともあったのかも知れません。 いずれにせよ、信頼挽回のための行動法としては、信頼されるようなスキル向上への実践あるのみです。 No.002さんの意識としても、「管理方法の把握からだと痛感」と具体的内容に方向づけられ、私としても社会人体験の中で本格的習得をした得意分野であり、その具体的実践内容のアドバイスへと向かいます。 一方道を歩く場面での視線恐怖症的状態は、これでほぼ完全解消です。 それが「気にしないように」といったアプローチではなく、むしろそれとは真逆の、「観察の客観性と正確さ」の徹底的探求によるものであるのが、お分かりかと思います。 ハイブリッド心理学の「感情と行動の分離」、そこで言う「感情を鵜呑みにしない」というのが、決して「感情を無視して理屈だけで」といったものではなく、新しい、より安定した感情の土台もしくは芯を築いていくことなのだ、と。 その結果、No.002さんの場合も、視線恐怖的感情がただ消えるのではなく、「色んな表情で歩く人がいるんですね」と、ごく素朴な好奇心という、より健全で穏やかな感情と入れ替わったというものになったわけです。 4回目アドバイスヘ 2015.5.14 |